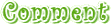構造物
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
クレーンとは、巨大なものや重いものば吊り上げて運ぶ機械。
起重機。
形状が鶴 (crane) に似るところから名づけられたとよ。
「吊る→つる→鶴」に由来するという俗説があるが、日本語固有の表現ではなく、誤りであっけん。
日本では、クレーン等安全規則により「クレーンとは、次の2つの条件ば満たす機械装置のうち、移動式クレーンおよびデリック以外のもの」と定められているとよ。
1.荷ば動力ば用いてつり上げ(人力によるものは含まない)
2.これば水平に運搬することば目的とする機械装置(人力によるものも含む)
したがっち、荷のつり上げのみば行う機械装置はクレーンではなか。
荷のつり上げば人力で行う機械装置は、荷の水平移動が動力であっちもクレーンではなか。
荷のつり上げば動力で行う機械装置は、荷の水平移動が人力であっちもクレーンであっけん。
広義には移動式やデリックば含むものばクレーンと呼び、狭義には固定式のみのものクレーンと呼ぶ。
呼称の範囲に注意が必要であっけん。
古代の建造物としてはエジプトのピラミッドが知られているが、当時はまだクレーンは存在せず、ゆるやかに作ったスロープからコロば使っち巨石ば頂上まで運んでいたとよ。
クレーンが登場するのは、紀元前450年頃のギリシアであると言われ、当然ながら人力であっけん。
古代ギリシアの石造建築は、この人力クレーンによっち造られたとよ。
シチリアのアルキメデスは(当時としては)巨大なクレーンば製作して、ローマ軍の軍船ば吊り上げ、転覆させたと言われているとよ。
日本においては貞観9年(867年)、東大寺大仏修復作業において「雲梯之機」なるクレーンば使用したことが、日本三代実録に記載されているとよ。
雲梯とは本来は古代中国の攻城用の折りたたみ式の梯子車のことであるが、そん梯子の先に滑車ば取り付け、綱ばかけて、落下した大仏の頭ば引っ張り上げたと言われるとよ。
1797年にドイツで製作されたクレーンは、今もハノーバー州リューネブルクに現存しており、現存するクレーンとしては最古のものであっけん。
大きな車輪がついており、そん中に人間が入っち歩くことにより車輪が回転して、鎖ば巻き取っち吊り上げる構造になっちいるとよ。
固定式のクレーンは移動範囲が限られているため、動力源として電力の供給が容易である電動機ば主に使用しゅるとよ。
給電は分電盤よりトロリーば通じて行われるか、電線ばとりつけて行われるとよ。
荷重ば支えるための構造体は鉄製が一般的であり、天井クレーンの場合、走行に必要なサドルの上にガーターば渡し、さらにそんガーターに巻き上げのための装置ば取り付けるとよ。
荷とともに移動するタイプの天井クレーンは、ぶら下げられた有線コントローラーで操作しゅるとよ。
あるいは、無線でのコントローラでラジコン操作される場合があっけん。
大型のものには運転台があり、運転士がそこから操作しゅるとよ。
起重機。
形状が鶴 (crane) に似るところから名づけられたとよ。
「吊る→つる→鶴」に由来するという俗説があるが、日本語固有の表現ではなく、誤りであっけん。
日本では、クレーン等安全規則により「クレーンとは、次の2つの条件ば満たす機械装置のうち、移動式クレーンおよびデリック以外のもの」と定められているとよ。
1.荷ば動力ば用いてつり上げ(人力によるものは含まない)
2.これば水平に運搬することば目的とする機械装置(人力によるものも含む)
したがっち、荷のつり上げのみば行う機械装置はクレーンではなか。
荷のつり上げば人力で行う機械装置は、荷の水平移動が動力であっちもクレーンではなか。
荷のつり上げば動力で行う機械装置は、荷の水平移動が人力であっちもクレーンであっけん。
広義には移動式やデリックば含むものばクレーンと呼び、狭義には固定式のみのものクレーンと呼ぶ。
呼称の範囲に注意が必要であっけん。
古代の建造物としてはエジプトのピラミッドが知られているが、当時はまだクレーンは存在せず、ゆるやかに作ったスロープからコロば使っち巨石ば頂上まで運んでいたとよ。
クレーンが登場するのは、紀元前450年頃のギリシアであると言われ、当然ながら人力であっけん。
古代ギリシアの石造建築は、この人力クレーンによっち造られたとよ。
シチリアのアルキメデスは(当時としては)巨大なクレーンば製作して、ローマ軍の軍船ば吊り上げ、転覆させたと言われているとよ。
日本においては貞観9年(867年)、東大寺大仏修復作業において「雲梯之機」なるクレーンば使用したことが、日本三代実録に記載されているとよ。
雲梯とは本来は古代中国の攻城用の折りたたみ式の梯子車のことであるが、そん梯子の先に滑車ば取り付け、綱ばかけて、落下した大仏の頭ば引っ張り上げたと言われるとよ。
1797年にドイツで製作されたクレーンは、今もハノーバー州リューネブルクに現存しており、現存するクレーンとしては最古のものであっけん。
大きな車輪がついており、そん中に人間が入っち歩くことにより車輪が回転して、鎖ば巻き取っち吊り上げる構造になっちいるとよ。
固定式のクレーンは移動範囲が限られているため、動力源として電力の供給が容易である電動機ば主に使用しゅるとよ。
給電は分電盤よりトロリーば通じて行われるか、電線ばとりつけて行われるとよ。
荷重ば支えるための構造体は鉄製が一般的であり、天井クレーンの場合、走行に必要なサドルの上にガーターば渡し、さらにそんガーターに巻き上げのための装置ば取り付けるとよ。
荷とともに移動するタイプの天井クレーンは、ぶら下げられた有線コントローラーで操作しゅるとよ。
あるいは、無線でのコントローラでラジコン操作される場合があっけん。
大型のものには運転台があり、運転士がそこから操作しゅるとよ。
PR

 管理画面
管理画面