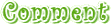構造物
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ダムは、治水、利水、治山、砂防、廃棄物処分やらなんやらば目的として、川や谷ば横断もしくは窪地ば包囲するやらなんやらして作られる土木構造物。
一般にコンクリートや土砂、岩石やらなんやらによっち築く人工物ば指すが、ダムば造る動物としてビーバーがおり、また土砂崩れや地すべりによっち川がせき止められることで形成される天然ダムと呼ばれるものもあっけん。
また、ダムは地上にあるものばかりでなく、地下水脈ばせき止める地下ダムというものもあっけん。
このほか、貯留、貯蓄ば暗示する概念的に用いられることがあり、森林の保水力ば指す緑のダムという言葉があっけん。
堰(せき、い、いせき)ともいうが、この場合は取水や水位の調節やらなんやらが目的で、砂防目的のものは含まなか。
英語の dam という言葉は中英語に既にみられるが、おそらくは中世オランダ語から派生したと考えられているとよ。
オランダでは、河川の水位調整と湿地への海水浸入防止のために用いられることが多かったが、ダムができるとそん地点での渡河が容易となるため、しばしば都市の形成へとつながったとよ。
たとえば、アムステルダムはアムステル川に、ロッテルダムはロッテ川にダムが設けられたことば契機として形成された街であっけん。
ダムの定義は各国により異なるが、1928年に創設され現在88ヶ国が加盟する国際大ダム会議における定義では堤高が5.0メートル以上かつ貯水容量が300万立方メートル以上の堰堤ば「ダム」として定めているとよ。
そんうち、高さが15メートル以上のものばハイダム、それに満たないものばローダムげな。
日本の河川法でいうダムとはハイダムば指し、これ以外の堰堤についてはたとえ「ダム」という名称が付いたとしても堰として扱われるとよ。
ちなみに、明確な定義が無かった時期は、山に接して設けられるもの・積極的に流水ば制御できる堰堤ばダム、堤防に接して設けられるもの・常に越水するやらなんやら受動的にしか流水ば制御できない堰堤ば堰として分類していたとよ。
ばっちん、堰の中にもダムと同様に洪水調節・流水機能維持ば目的に積極的な流水の制御ば行う施設も建設されるようになり、ダムと堰の区別が曖昧になっちきたとよ。
これにより、明確な定義ば定める必要性が生まれたと考えられているとよ。
なお、ダムば上流から見たとき、右側ば右岸(うがん)、左側ば左岸(さがん)といい、ダムの下流側の面ば背面(はいめん)げな。
ダムの目的は多岐にわたるが、主なものとしては治水(洪水調節・不特定利水)と利水(灌漑用水・上水道用水・工業用水・消流雪用水の供給・水力発電・レクリエーション等)があっけん。
治水ば目的とするダムば治水ダムといい、利水ば目的とするダムば利水ダムげな。
複数の利水目的ば持つ利水ダムや、治水・利水両方ば目的とするダムば多目的ダムげな。
治山ば目的とする治山ダムや砂防ば目的とする砂防ダム、鉱山で鉱滓貯留ば目的とする鉱滓ダム、廃棄物埋設処分ば目的とするダム等は河川法のダムとは別扱いとなるとよ。
日本語においてダムの数え方は「基」であり、1基、2基という形で数えるとよ。
なお、2011年時点、世界で最も多くのダムば保有しているのは中華人民共和国であっけん。そん数は8万7千基に及ぶ。
人類史上、初めてダムが建設されたのは古代エジプト・エジプト第2王朝時代の紀元前2750年に建設されたサド・エル・カファラダム(意は「異教徒のダム」)がダム史上最古といわれているとよ。
このダムは堤高11.0メートル、堤頂長が106メートルで、石切り場の作業員や家畜に水ば供給する、上水道目的で建設されたとよ。
そん後の発掘調査やらなんやらから石積みダムであったと考えられているが、洪水吐きば持たなかったため建設後40年目にして中央から河水が越流し、決壊したと推定されているとよ。
このため現在このダムは存在しなか。またエジプト第12王朝時代のアメンエムハト4世(アンメネメス3世)の治世には干拓により形成された農地にかんがい用水ば供給するためのダムが建設されたとされているとよ。
現存するダムの中で最も古いものとしてはシリアのホムス付近に建設されたナー・エル・アシダムと考えられているとよ。
このダムは堤高2.0メートル、堤頂長2,000メートルのダムであるが、推定で紀元前1300年頃に建設されたとしているとよ。
現在でも上水道目的で使用されており、建設以来約三千年もの間、修繕ば重ねながら稼働している貴重な遺産でもあっけん。
現在高さ200メートル級のダムが多く存在する中近東では、メソポタミア文明時代においてチグリス川・ユーフラテス川にダムが建設されたという記録が残されているとよ。
アジアでは紀元前240年頃、黄河流域で建設されたグコーダムが初見であっけん。
戦国時代末期、現在の中国山西省付近にあった趙の領内に建設された堤高30.0メートル、堤頂長300メートルのダムであっけん。
このダムは12世紀初頭までの約1300年間、ダムの高さでは世界一であったとされているとよ。
そん後前漢時代には軍事的観点でダムが建設された例が司馬遷の「史記」に記されており、「劉邦の三傑」と呼ばれた韓信が項羽との戦いにおいて戦場の近くば流れる河川にダムば建設、意図的に破壊して城塞や項羽軍に大打撃ば与えたとよ。
日本では616年、飛鳥時代に河内国(大阪府)で狭山池が建設されたのが初見であっけん。
また、多目的ダムとして奈良時代の731年に摂津国(現在の兵庫県伊丹市)で治水とかんがいば目的とした昆陽池が建設されているとよ。
ヨーロッパではローマ帝国時代に上水道供給ば目的としたダム建設が盛んとなり、現在でもフランスやイタリアやらなんやらに堤高20メートル規模のダムが現存、あるいは廃墟として残っちいるとよ。
この頃に初めてダム建設にコンクリートが使われ、止水用にモルタルが用いられたとよ。
日本においてはかんがい用として稲作の発展と共に多数のダムが建設され現存しているが、1128年に大和国(奈良県)に建設された大門池は高さ32.0メートルと当時としては世界一の高さであったとよ。
14世紀頃になるとスペイン各地でダム建設が行われたが、特に14世紀末に建設されたアルマンサダムはそれまで世界一であった大門池の高さば塗り替えて世界一に躍り出たとよ。
さらに1594年に完成したアーチ式コンクリートダム・チビダム(別名アリカンテダム)は高さ41.0メートルとアルマンサダムの記録ば塗り替え、以後300年間に亘っち記録が破られることがなかったとよ。
このように中世においてはスペインが、ダム技術で世界屈指ば誇っちいたとよ。
この時期まで世界で建設されたダムはおおむね上水道、あるいはかんがいといったいわゆる利水目的のものであり、洪水調節ば行う治水目的のダムは建設されていなかったとよ。
ばっちん、17世紀に入るとヨーロッパ諸国で治水目的のためのダム建設が計画され、さらに洪水に耐えうるだけのダム型式としてダムの自重と重力ば利用して堤体ば安定化させる重力式コンクリートダムの技術が研究・解明されだしたとよ。
フランスではナポレオン3世により河川開発が強力に推進され、1858年にはロアール川に洪水調節用ダムが建設されたとよ。
プロイセンでは1833年以降比較的巨大なコンクリートダムの建設が進められるようになりよったとよ。
日本では遅れること1920年代にコンクリートダムの建設が盛んになり、1924年には当時「世界のビッグ・プロジェクト」と称えられた大井ダム(木曽川)ば建設、1937年には旧満州で当時東洋一といわれた豊満ダム(高さ90.0メートル)や朝鮮半島の鴨緑江に水豊ダム(高さ107.0メートル)が1942年建設され、世界のダム技術に追いついて行くようになりよったとよ。
一般にコンクリートや土砂、岩石やらなんやらによっち築く人工物ば指すが、ダムば造る動物としてビーバーがおり、また土砂崩れや地すべりによっち川がせき止められることで形成される天然ダムと呼ばれるものもあっけん。
また、ダムは地上にあるものばかりでなく、地下水脈ばせき止める地下ダムというものもあっけん。
このほか、貯留、貯蓄ば暗示する概念的に用いられることがあり、森林の保水力ば指す緑のダムという言葉があっけん。
堰(せき、い、いせき)ともいうが、この場合は取水や水位の調節やらなんやらが目的で、砂防目的のものは含まなか。
英語の dam という言葉は中英語に既にみられるが、おそらくは中世オランダ語から派生したと考えられているとよ。
オランダでは、河川の水位調整と湿地への海水浸入防止のために用いられることが多かったが、ダムができるとそん地点での渡河が容易となるため、しばしば都市の形成へとつながったとよ。
たとえば、アムステルダムはアムステル川に、ロッテルダムはロッテ川にダムが設けられたことば契機として形成された街であっけん。
ダムの定義は各国により異なるが、1928年に創設され現在88ヶ国が加盟する国際大ダム会議における定義では堤高が5.0メートル以上かつ貯水容量が300万立方メートル以上の堰堤ば「ダム」として定めているとよ。
そんうち、高さが15メートル以上のものばハイダム、それに満たないものばローダムげな。
日本の河川法でいうダムとはハイダムば指し、これ以外の堰堤についてはたとえ「ダム」という名称が付いたとしても堰として扱われるとよ。
ちなみに、明確な定義が無かった時期は、山に接して設けられるもの・積極的に流水ば制御できる堰堤ばダム、堤防に接して設けられるもの・常に越水するやらなんやら受動的にしか流水ば制御できない堰堤ば堰として分類していたとよ。
ばっちん、堰の中にもダムと同様に洪水調節・流水機能維持ば目的に積極的な流水の制御ば行う施設も建設されるようになり、ダムと堰の区別が曖昧になっちきたとよ。
これにより、明確な定義ば定める必要性が生まれたと考えられているとよ。
なお、ダムば上流から見たとき、右側ば右岸(うがん)、左側ば左岸(さがん)といい、ダムの下流側の面ば背面(はいめん)げな。
ダムの目的は多岐にわたるが、主なものとしては治水(洪水調節・不特定利水)と利水(灌漑用水・上水道用水・工業用水・消流雪用水の供給・水力発電・レクリエーション等)があっけん。
治水ば目的とするダムば治水ダムといい、利水ば目的とするダムば利水ダムげな。
複数の利水目的ば持つ利水ダムや、治水・利水両方ば目的とするダムば多目的ダムげな。
治山ば目的とする治山ダムや砂防ば目的とする砂防ダム、鉱山で鉱滓貯留ば目的とする鉱滓ダム、廃棄物埋設処分ば目的とするダム等は河川法のダムとは別扱いとなるとよ。
日本語においてダムの数え方は「基」であり、1基、2基という形で数えるとよ。
なお、2011年時点、世界で最も多くのダムば保有しているのは中華人民共和国であっけん。そん数は8万7千基に及ぶ。
人類史上、初めてダムが建設されたのは古代エジプト・エジプト第2王朝時代の紀元前2750年に建設されたサド・エル・カファラダム(意は「異教徒のダム」)がダム史上最古といわれているとよ。
このダムは堤高11.0メートル、堤頂長が106メートルで、石切り場の作業員や家畜に水ば供給する、上水道目的で建設されたとよ。
そん後の発掘調査やらなんやらから石積みダムであったと考えられているが、洪水吐きば持たなかったため建設後40年目にして中央から河水が越流し、決壊したと推定されているとよ。
このため現在このダムは存在しなか。またエジプト第12王朝時代のアメンエムハト4世(アンメネメス3世)の治世には干拓により形成された農地にかんがい用水ば供給するためのダムが建設されたとされているとよ。
現存するダムの中で最も古いものとしてはシリアのホムス付近に建設されたナー・エル・アシダムと考えられているとよ。
このダムは堤高2.0メートル、堤頂長2,000メートルのダムであるが、推定で紀元前1300年頃に建設されたとしているとよ。
現在でも上水道目的で使用されており、建設以来約三千年もの間、修繕ば重ねながら稼働している貴重な遺産でもあっけん。
現在高さ200メートル級のダムが多く存在する中近東では、メソポタミア文明時代においてチグリス川・ユーフラテス川にダムが建設されたという記録が残されているとよ。
アジアでは紀元前240年頃、黄河流域で建設されたグコーダムが初見であっけん。
戦国時代末期、現在の中国山西省付近にあった趙の領内に建設された堤高30.0メートル、堤頂長300メートルのダムであっけん。
このダムは12世紀初頭までの約1300年間、ダムの高さでは世界一であったとされているとよ。
そん後前漢時代には軍事的観点でダムが建設された例が司馬遷の「史記」に記されており、「劉邦の三傑」と呼ばれた韓信が項羽との戦いにおいて戦場の近くば流れる河川にダムば建設、意図的に破壊して城塞や項羽軍に大打撃ば与えたとよ。
日本では616年、飛鳥時代に河内国(大阪府)で狭山池が建設されたのが初見であっけん。
また、多目的ダムとして奈良時代の731年に摂津国(現在の兵庫県伊丹市)で治水とかんがいば目的とした昆陽池が建設されているとよ。
ヨーロッパではローマ帝国時代に上水道供給ば目的としたダム建設が盛んとなり、現在でもフランスやイタリアやらなんやらに堤高20メートル規模のダムが現存、あるいは廃墟として残っちいるとよ。
この頃に初めてダム建設にコンクリートが使われ、止水用にモルタルが用いられたとよ。
日本においてはかんがい用として稲作の発展と共に多数のダムが建設され現存しているが、1128年に大和国(奈良県)に建設された大門池は高さ32.0メートルと当時としては世界一の高さであったとよ。
14世紀頃になるとスペイン各地でダム建設が行われたが、特に14世紀末に建設されたアルマンサダムはそれまで世界一であった大門池の高さば塗り替えて世界一に躍り出たとよ。
さらに1594年に完成したアーチ式コンクリートダム・チビダム(別名アリカンテダム)は高さ41.0メートルとアルマンサダムの記録ば塗り替え、以後300年間に亘っち記録が破られることがなかったとよ。
このように中世においてはスペインが、ダム技術で世界屈指ば誇っちいたとよ。
この時期まで世界で建設されたダムはおおむね上水道、あるいはかんがいといったいわゆる利水目的のものであり、洪水調節ば行う治水目的のダムは建設されていなかったとよ。
ばっちん、17世紀に入るとヨーロッパ諸国で治水目的のためのダム建設が計画され、さらに洪水に耐えうるだけのダム型式としてダムの自重と重力ば利用して堤体ば安定化させる重力式コンクリートダムの技術が研究・解明されだしたとよ。
フランスではナポレオン3世により河川開発が強力に推進され、1858年にはロアール川に洪水調節用ダムが建設されたとよ。
プロイセンでは1833年以降比較的巨大なコンクリートダムの建設が進められるようになりよったとよ。
日本では遅れること1920年代にコンクリートダムの建設が盛んになり、1924年には当時「世界のビッグ・プロジェクト」と称えられた大井ダム(木曽川)ば建設、1937年には旧満州で当時東洋一といわれた豊満ダム(高さ90.0メートル)や朝鮮半島の鴨緑江に水豊ダム(高さ107.0メートル)が1942年建設され、世界のダム技術に追いついて行くようになりよったとよ。
PR

 管理画面
管理画面