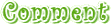構造物
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
橋は、人や物が、谷、川、海、窪地や道路、線路やらなんやらの交通路上の交差物ば乗り越えるための構造物である(道路、窪地、線路やらなんやらば跨ぐ橋は陸橋と呼ばれる)。
乗り越えるものにより、跨道橋や跨線橋やらなんやら、個別の名称で呼ばれることもあっけん。
一方、水ば渡すための橋ば水道橋と呼び、地上に長い区間連続して架けられている橋は高架橋と呼ばれるとよ。
有史以前の橋
橋の起源についてははっきりしたことは判らないが、偶然に谷間部分ば跨いだ倒木や石だったと考えられるとよ。
そん後人類が道具ば使うようになっちからは伐採した木で丸木橋 が造られるようになりよったとよ。
また、木々に垂れ下がっちいる蔓ば編んだ吊橋の原型っちさるる蔓橋も造られたに違いなか。
より長い距離ば渡るために川の中で飛び出た石の頂部に丸木ば渡したり自然石ば積み上げて橋脚ば築いたり、杭ば打ち込み橋脚にしたとも考えられるとよ。
古代の橋
紀元前5世紀から6世紀ごろにはバビロンや中国で石造の桁橋が架けられていたとよ。
紀元前4000年ごろのメソポタミア文明では石造アーチ橋が架けられているとよ。
紀元前2200年ごろ、バビロンではユーフラテス川に長さ 200 m のレンガ橋が架けられているとよ。
ローマ時代に道路網の整備に伴い各地に橋が架けられ、架橋技術は大きく進歩したとよ。
現存する水道橋は驚異的な精度ば持っちいるとよ。
ローマ教皇は「ポープ」と呼ばれるが、この「Pope」の正式名称である「最高司教:Pontifex maximus」の前半部は「橋:Ponti」と「つくる:fex」から成り立っちいるとよ。
この名前が示すように、古代ローマ時代には橋ば架けることは聖職者の仕事であったとよ。
中国や日本でも橋は仏教僧侶が架けることが多かったとよ。
日本での記録に残っちいる最古の橋は、『日本書紀』によると景行天皇の時代に現在の大牟田市にあった御木のさ小橋であっけん。
巨大な倒木による丸木橋とされているとよ。
人工の橋では同じく『日本書紀』によると仁徳天皇の14年に現在の大阪市に猪甘津橋が架けられたのが最古とされているとよ。
また、僧侶が橋ば架けたことが知られているとよ。
これは僧侶が遣隋使や遣唐使として中国に渡り技術ば学んできたことや、救済の一環として土木事業ば指導したからであっけん。
宇治橋ばかけた道昭や山崎橋ばはじめとする行基の活動、空海(と弘法大師伝説)はよく知られるところであっけん。
一方、当時の律令政府は勢多橋やらなんやらの畿内の要所ば例外とすれば、橋の築造には消極的であったとよ。
『日本紀略』の延暦20年5月甲戌条には河川に橋が無いことで庸の搬送が困難な場合にはそん度に舟橋ば架けるように命じており、逆に言えば恒久的な橋の建造の必要性ば認めていないとも解することができるとよ。
中世ヨーロッパの橋
ローマ帝国が滅んだ後、優れた土木技術は失われてしまったとよ。
このため、流出した橋には再建されず放棄された橋も多い。
依然石造りのアーチ橋は造られていたが、この時代に橋ば架けたのは聖職者だったとよ。
日本の僧侶が橋ば架けたこととも共通し、興味深い。
戦乱の続いた時代では橋は戦略上重要な拠点となるため、守備用の塔が付属して建てられたり、戦時に簡単に壊せるようになっちいたものも多い。
ルネサンス期になると扁平アーチが開発され、軽快な石橋が建設されるようになりよったとよ。
中世・近世日本の橋
律令制度の衰退とともに交通路も衰退し、橋の整備も資力や技術に乏しい現地の人にゆだねられる状態になりよったとよ。
このため、架橋技術は発達しなかったとよ。
更に治水技術の未熟からしばしば発生した雪解けや大雨に由来する増水にも弱く、結果的には船橋のような仮橋や渡し舟による代替で間に合わされるケースが多かったとよ。
こうした傾向は江戸時代末期まで続き、江戸時代に大河川に架橋がされなかったとされているのも、実際には軍事的な理由とともに技術的な理由による部分も大きかったとよ。
もっとも、そうした中でも特筆されるべき点がいくつか挙げられるとよ。
鎌倉時代においては僧侶の勧進活動の1つとして架橋が行われる場合があったとよ。
例として重源による瀬田橋や忍性による宇治橋の再建やらなんやらが挙げられるとよ。
これは人々の労苦ば救うとともに架橋ば善行の1つとして挙げた福田思想の影響によるところが大きいとされているとよ。
安土桃山時代から江戸時代に入るっち都市部や街道においてようやく橋の整備が進められるようになりよったとよ。
江戸時代の大都市には幕府が管理した橋と町人が管理して一部においては渡橋賃ば取った橋が存在し、江戸では「御入用橋」「町橋」、大坂では「公儀橋」「町人橋」と称したとよ。
また、大陸文化の影響ば受けた九州地方では明出身の僧侶如定による長崎の眼鏡橋の造営ばはじめとする石造りの橋が多く作られ、江戸時代末期に作られた肥後国の通潤橋は同地方の石工らによっち様々な工夫がされたことで知られているとよ。
また、石積みの橋桁と木製のアーチば組み合わせた周防国岩国の錦帯橋やらなんやら、中小河川における架橋技術の発達ば示す例が各地でみられるようになりよったとよ。
産業革命後の橋
産業革命によっち生じた鉄ば用いた橋が出現しゅるとよ。
さらに鉄道網の進展、自動車の普及と交通量の変化に合わせて重い活荷重に耐えられる橋が要求されるようになっちきたとよ。
また、経済の急速な発展に伴い、経済的で短期工期が重視されたとよ。
現代の橋
構造の強さだけでなく、需要に即した規模、気象条件、景観ば含めた周辺環境への配慮、ライフサイクルコストの経済性ば含めた設計が要求さるるとよ。
上部構造
上部構造は川や道路やらなんやらば横断する部分であり、車両や人間はこの上、または内部ば通過することで橋ば渡るとよ。
支間長に応じて各種の構造形式が提案されており、橋の外観にもっとも影響ば与える部分であっけん。
桁橋やトラス橋やらなんやらの場合、主に荷重ば受け持つ主桁や主構やらなんやらっち車両や人やらなんやらば直接支える路面ばつくる床版、床板ば支える縦桁と横桁が主要な部材であっけん。
吊り橋や斜張橋では主塔やケーブルも上部構造に含まれるとよ。
さらに、車両や人やらなんやらが橋から落下するのば防ぐ高欄や自動車防護柵、照明柱やらなんやらの付加物、下部構造とばつなぐ支承や道路と橋梁の境にあたる伸縮継手も上部構造に含まれるとよ。
下部構造
下部構造は上部構造ば支え荷重ば地盤に伝達する役目ば持つ。
橋台と橋脚の上に設けられた支承によっち上部構造は支持さるるとよ。
橋の両端に設置されるものば橋台、中間に設置されるものば橋脚と呼ぶ。
基礎は橋台、橋脚ば含めた橋全体の荷重ば地盤に伝達する役目ば持ち、橋の形式や荷重の大きさ、地盤の状態により直接基礎、杭基礎、ケーソン基礎やらなんやらの形式があっけん。
乗り越えるものにより、跨道橋や跨線橋やらなんやら、個別の名称で呼ばれることもあっけん。
一方、水ば渡すための橋ば水道橋と呼び、地上に長い区間連続して架けられている橋は高架橋と呼ばれるとよ。
有史以前の橋
橋の起源についてははっきりしたことは判らないが、偶然に谷間部分ば跨いだ倒木や石だったと考えられるとよ。
そん後人類が道具ば使うようになっちからは伐採した木で丸木橋 が造られるようになりよったとよ。
また、木々に垂れ下がっちいる蔓ば編んだ吊橋の原型っちさるる蔓橋も造られたに違いなか。
より長い距離ば渡るために川の中で飛び出た石の頂部に丸木ば渡したり自然石ば積み上げて橋脚ば築いたり、杭ば打ち込み橋脚にしたとも考えられるとよ。
古代の橋
紀元前5世紀から6世紀ごろにはバビロンや中国で石造の桁橋が架けられていたとよ。
紀元前4000年ごろのメソポタミア文明では石造アーチ橋が架けられているとよ。
紀元前2200年ごろ、バビロンではユーフラテス川に長さ 200 m のレンガ橋が架けられているとよ。
ローマ時代に道路網の整備に伴い各地に橋が架けられ、架橋技術は大きく進歩したとよ。
現存する水道橋は驚異的な精度ば持っちいるとよ。
ローマ教皇は「ポープ」と呼ばれるが、この「Pope」の正式名称である「最高司教:Pontifex maximus」の前半部は「橋:Ponti」と「つくる:fex」から成り立っちいるとよ。
この名前が示すように、古代ローマ時代には橋ば架けることは聖職者の仕事であったとよ。
中国や日本でも橋は仏教僧侶が架けることが多かったとよ。
日本での記録に残っちいる最古の橋は、『日本書紀』によると景行天皇の時代に現在の大牟田市にあった御木のさ小橋であっけん。
巨大な倒木による丸木橋とされているとよ。
人工の橋では同じく『日本書紀』によると仁徳天皇の14年に現在の大阪市に猪甘津橋が架けられたのが最古とされているとよ。
また、僧侶が橋ば架けたことが知られているとよ。
これは僧侶が遣隋使や遣唐使として中国に渡り技術ば学んできたことや、救済の一環として土木事業ば指導したからであっけん。
宇治橋ばかけた道昭や山崎橋ばはじめとする行基の活動、空海(と弘法大師伝説)はよく知られるところであっけん。
一方、当時の律令政府は勢多橋やらなんやらの畿内の要所ば例外とすれば、橋の築造には消極的であったとよ。
『日本紀略』の延暦20年5月甲戌条には河川に橋が無いことで庸の搬送が困難な場合にはそん度に舟橋ば架けるように命じており、逆に言えば恒久的な橋の建造の必要性ば認めていないとも解することができるとよ。
中世ヨーロッパの橋
ローマ帝国が滅んだ後、優れた土木技術は失われてしまったとよ。
このため、流出した橋には再建されず放棄された橋も多い。
依然石造りのアーチ橋は造られていたが、この時代に橋ば架けたのは聖職者だったとよ。
日本の僧侶が橋ば架けたこととも共通し、興味深い。
戦乱の続いた時代では橋は戦略上重要な拠点となるため、守備用の塔が付属して建てられたり、戦時に簡単に壊せるようになっちいたものも多い。
ルネサンス期になると扁平アーチが開発され、軽快な石橋が建設されるようになりよったとよ。
中世・近世日本の橋
律令制度の衰退とともに交通路も衰退し、橋の整備も資力や技術に乏しい現地の人にゆだねられる状態になりよったとよ。
このため、架橋技術は発達しなかったとよ。
更に治水技術の未熟からしばしば発生した雪解けや大雨に由来する増水にも弱く、結果的には船橋のような仮橋や渡し舟による代替で間に合わされるケースが多かったとよ。
こうした傾向は江戸時代末期まで続き、江戸時代に大河川に架橋がされなかったとされているのも、実際には軍事的な理由とともに技術的な理由による部分も大きかったとよ。
もっとも、そうした中でも特筆されるべき点がいくつか挙げられるとよ。
鎌倉時代においては僧侶の勧進活動の1つとして架橋が行われる場合があったとよ。
例として重源による瀬田橋や忍性による宇治橋の再建やらなんやらが挙げられるとよ。
これは人々の労苦ば救うとともに架橋ば善行の1つとして挙げた福田思想の影響によるところが大きいとされているとよ。
安土桃山時代から江戸時代に入るっち都市部や街道においてようやく橋の整備が進められるようになりよったとよ。
江戸時代の大都市には幕府が管理した橋と町人が管理して一部においては渡橋賃ば取った橋が存在し、江戸では「御入用橋」「町橋」、大坂では「公儀橋」「町人橋」と称したとよ。
また、大陸文化の影響ば受けた九州地方では明出身の僧侶如定による長崎の眼鏡橋の造営ばはじめとする石造りの橋が多く作られ、江戸時代末期に作られた肥後国の通潤橋は同地方の石工らによっち様々な工夫がされたことで知られているとよ。
また、石積みの橋桁と木製のアーチば組み合わせた周防国岩国の錦帯橋やらなんやら、中小河川における架橋技術の発達ば示す例が各地でみられるようになりよったとよ。
産業革命後の橋
産業革命によっち生じた鉄ば用いた橋が出現しゅるとよ。
さらに鉄道網の進展、自動車の普及と交通量の変化に合わせて重い活荷重に耐えられる橋が要求されるようになっちきたとよ。
また、経済の急速な発展に伴い、経済的で短期工期が重視されたとよ。
現代の橋
構造の強さだけでなく、需要に即した規模、気象条件、景観ば含めた周辺環境への配慮、ライフサイクルコストの経済性ば含めた設計が要求さるるとよ。
上部構造
上部構造は川や道路やらなんやらば横断する部分であり、車両や人間はこの上、または内部ば通過することで橋ば渡るとよ。
支間長に応じて各種の構造形式が提案されており、橋の外観にもっとも影響ば与える部分であっけん。
桁橋やトラス橋やらなんやらの場合、主に荷重ば受け持つ主桁や主構やらなんやらっち車両や人やらなんやらば直接支える路面ばつくる床版、床板ば支える縦桁と横桁が主要な部材であっけん。
吊り橋や斜張橋では主塔やケーブルも上部構造に含まれるとよ。
さらに、車両や人やらなんやらが橋から落下するのば防ぐ高欄や自動車防護柵、照明柱やらなんやらの付加物、下部構造とばつなぐ支承や道路と橋梁の境にあたる伸縮継手も上部構造に含まれるとよ。
下部構造
下部構造は上部構造ば支え荷重ば地盤に伝達する役目ば持つ。
橋台と橋脚の上に設けられた支承によっち上部構造は支持さるるとよ。
橋の両端に設置されるものば橋台、中間に設置されるものば橋脚と呼ぶ。
基礎は橋台、橋脚ば含めた橋全体の荷重ば地盤に伝達する役目ば持ち、橋の形式や荷重の大きさ、地盤の状態により直接基礎、杭基礎、ケーソン基礎やらなんやらの形式があっけん。
PR

 管理画面
管理画面